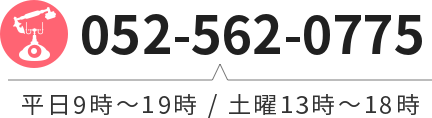大まかに言うと、次のような流れとなります。
①債務名義を取得する
②差し押さえ可能な財産について情報を収集する
③強制執行を申し立てる
④差し押さえの効力発生
⑤直接取り立てる(債権差し押さえの場合)

解説
1.債務名義の取得
強制執行をするためには、債務名義が必要です。
債務名義とは、債務の存在と具体的内容を明らかにする文書であり、法律で債務名義と定められているものです。具体的には確定した判決、審判書、調停調書、執行認諾文言付きの公正証書などです(民事執行法22条)。
養育費の場合、調停で取り決めたなら調停調書、調停から審判となって支払額が決まったならば審判書、裁判所に行かず公正証書で取り決めたならば公正証書(執行認諾文言付きのものに限りますが、通常は付けているはずです。)が債務名義に当たります。
単なる合意書など債務名義にならない形式で取り決めている場合、または取り決めをしていない場合、強制執行の申立てをするためには、まず債務名義を取得する必要があります。債務名義取得のためには、養育費請求の調停を申し立てるのが一般的です。
債務名義が存在する場合でも、強制執行を申し立てる前に、以下のような一定の手続きが必要です。いずれも債務名義を作成した裁判所または公証役場に申請することができます。
- 執行文の付与(判決や公正証書等の場合)
- 確定証明書の取得(審判等の場合)
- 送達証明書の取得(つねに必要)
- 送達申請(まだ送達されていない場合)
2.差し押さえ可能な財産の情報収集・把握
強制執行は、相手の財産を強制的に換価して(お金に換えて)債権を満足させる手続きです。裁判所に対して、相手のどの財産について強制執行を求めるのかを特定して申し立てる必要があります。
そこで、お金を効率的に回収できそうな相手の財産を探索するとともに、その財産について申し立てに必要な情報を収集する必要があります。
たとえば、将来の月々の養育費を相手の給与から回収できそうであれば、給与債権を差し押さえる方針として、その給与の支払い者である会社の名称や住所を調査します。あるいは、未払いの養育費を預貯金から回収できそうであれば、預貯金債権を差し押さえる方針として、その預貯金の金融機関名と支店名を調査します。
必要な情報収集について詳しくは、よくあるご質問「強制執行をするためには、相手のどのような情報が必要ですか。」をご参照ください。
給与の差押さえについて詳しくは、よくあるご質問「給料の差し押さえはできますか。注意すべきことはありますか。」をご参照ください。
3.強制執行の申立て
管轄のある地方裁判所に、強制執行を申し立てます。管轄は差し押さえる財産によって異なり、不動産の差し押さえであれば不動産の所在地、給与や預貯金などの債権の差し押さえであれば基本的には相手の住所地の裁判所となります。
申立ては、債権執行申立書など差し押さえる財産の種類に応じた形式の申立書と債務名義、および所定の必要書類を提出して行います。
債権差し押さえの必要書類の例
- 送達証明書(債務名義が送達されたことの証明書)
- 第三債務者の資格証明書(給与なら勤務先会社の登記事項証明書、預貯金なら金融機関の登記事項証明書)
- 相手の住民票(債務名義から住所が変わっている場合)
また、申立てに際して所定の額の収入印紙や郵便切手を納付する必要があります。
4.差し押さえの効力発生
債権差し押さえの場合、申し立てに不備がなければ、裁判所が差押命令を発します。この差押命令は債務者(相手)と第三債務者(給与なら勤務先会社、預貯金なら金融機関)に送達されます。第三債務者に送達されたときに、差し押さえの効力が発生すると定められています(民事執行法145条5項)。
差し押さえの効力発生により、債務者は差押債権を取り立てることができなくなり、第三債務者は差押債権を債務者に弁済することができなくなります。つまり、給与であれば相手は会社から給与を受け取ってはならず、会社も相手に支払ってはならないという効果が発生します(ただし、養育費の場合、給与について差し押さえることができるのは手取り額の2分の1まで)。
5.差押債権の取り立て
養育費の強制執行の場合、差押命令の送達から1週間が経過すると、債権者による取り立てが可能になります(民事執行法155条1項・2項括弧書)。
取り立てとは、相手の代わりにこちらに払ってもらうことです。給与であれば相手の勤務先会社に連絡し、支払方法を伝えて支払いを受けることができます。将来の給与も差し押さえた場合には、以後継続的に会社からの支払いを受けていくことになります。
会社が支払いを拒否する場合については、よくあるご質問「養育費回収のために相手の給料を差し押さえる場合に、会社から拒否されることもありますか。拒否されたらどうすればよいですか。」をご参照ください。
取り立てに成功した場合、裁判所に対して取立届を提出します。継続的に取り立てる場合、毎月の支払いの都度提出する必要があることに注意が必要です。