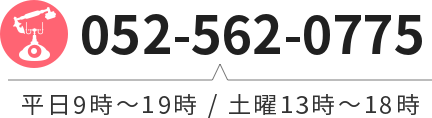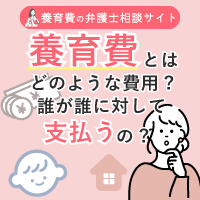成人年齢引き下げにより、養育費の法的な支払い義務の終期が早まることはなく、これまでどおり子供が「未成熟子」でなくなるまで支払い義務があります。実務上も、これまでどおり20歳を中心におおむね18歳から22歳(大学卒業時)までの間で、事案により個別に判断されることになります。

目次
1.成年(成人)年齢引き下げとは
2022年4月1日に民法の一部について改正法が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
|
(旧)民法4条 年齢20歳をもって、成年とする。 |
↓
|
(新)民法4条 年齢18歳をもって、成年とする。 |
成年に達していない「未成年者」は、法律行為に法定代理人の同意が必要であり、単独で行った法律行為は法定代理人が取り消すことができるという行為能力の制限を受けています。この制限が、成年年齢引き下げにより18歳と19歳については撤廃されます。つまり、以前は18歳や19歳の方が勝手に締結してしまった契約は親が取り消すことができましたが、今後はできなくなります。
2.養育費への影響
少しわかりにくいところですが、養育費は未成年の子供のための監護養育費用というわけではありません。親が親権者であるかどうかにかかわらず、また子供が未成年であるかどうかにかかわらず、親は自分の子供が未成熟である間は子供に対する扶養義務を負っており、それを親同士の間で分担するのが養育費です。
「未成年」であることと「未成熟」であることは、同じではありません。「未成年」かどうかは一律に年齢で決まるのに対し、「未成熟」であるかどうかはその子供の能力(とくに働いて収入を得る能力)や家庭環境、親の意思などの事情によって異なってきます。実務上は20歳を未成熟子の基準とすることが多いものの、おおむね18歳から22歳(大学卒業時)までの間で事案により判断されています。
この枠組みは、成年年齢引き下げによって影響を受けません。成年年齢が18歳になっても、これまでどおり子供が「未成熟」である間は養育費の支払い義務があり、それが具体的に何歳までかは個別に判断されることになります。
3.養育費の取決めがある場合
(1)確定期限を定めていた場合
「20歳の誕生日の属する月まで」「2024年3月まで」などの表現で、客観的に明らかな終期を定めていた場合には、文言通りの支払い義務が継続します。
(2)「成年に達するまで」と定めていた場合
「成年に達するまで」としていた場合は、成年年齢引き下げにより終期が変わってしまうように思われるかもしれませんが、そうではありません。
養育費を取り決めた当時、成年は20歳のことを指していたのであり、当事者はその認識で取り決めているため、解釈により「成年」=「20歳」と読み替えて養育費の支払い義務が継続することになります。
法務省も同様の見解を公表しています。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00230.html
(3)変更を申し立てられたら
成年年齢が引き下げられたことを理由に養育費の終期について変更を求めても、認められないと考えられます。取決めの前提となっているのはいつまで「未成年」かではなく、いつまで「未成熟」かであり、その点に関する事情変更があるとはいえないからです。
4.養育費の取決めがない場合
これから取決めをする、あるいは家庭裁判所で判断してもらうという場合には、前述のとおり、成人年齢引き下げにより、養育費の法的な支払い義務の終期が早まることはなく、これまでどおり子供が「未成熟子」でなくなるまで支払い義務があります。実務上も、これまでどおり20歳を中心におおむね18歳から22歳(大学卒業時)までの間で、事案により個別に判断されることになります。