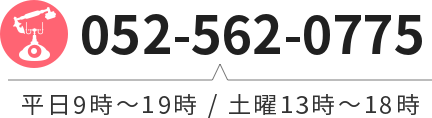A.公正証書を作るには、公証役場に公正証書作成の申し込みをし、当事者同士で決めた合意内容を伝えて、必要書類を提出します。公証人が案文を作成しますから、それを事前に確認します。作成日を決め、その日時に当事者が公証役場に集まります。公証人が文書を読み上げ、各当事者が署名・押印し、最後に公証人が署名・押印して完成します。その後、費用を支払い、正本の交付を受けます。

解説
1.公正証書はどこで作成するのか
(1)全国の公証役場
公正証書は公証人が作成する文書です。公証人の執務場所は公証役場といい、全国各地にあります。名古屋市には3か所あります。裁判所と違い、管轄による利用制限はないので、住所等にかかわらず、利用しやすいところを選べばよいでしょう。
(2)公正証書は自分で作れる?
離婚の協議書や養育費に関する合意書を自分たちだけで作ることはもちろんできますが、公正証書にするには必ず公証人の関与が必要です。それも、単に自分たちだけで作った文書を持って行って手続を通せば公正証書となる、というものではありません。本人確認と内容の確認を慎重に行ったうえで、同じ内容の文書を公証人が作り直すもの、と理解しましょう。
公正証書の意味やメリットについては、「よくある質問:養育費の取り決めを公正証書にするメリットはなんですか。」をご参照ください。
2.養育費の公正証書の必要書類
当事者双方が出頭できる場合には、一般に、次のような書類が必要になります。一方が出頭できない場合にはこのほかに委任状などが必要です。詳しくは、利用する予定の公証役場に確認してください。
①合意内容を記載した文書
自分たちで作った離婚協議書や養育費に関する合意書はこれに当たります。しかし書き方は自由で、きちんとした文書の形にしておく必要はなく、メモでも十分です。
②本人確認書類
印鑑証明書と実印、または顔写真つきの運転免許証などです。
③戸籍謄本
夫婦の婚姻関係、子供との親子関係を確認するためです。
3.養育費の公正証書の費用
公正証書の費用は、法令で決められています。したがって、全国どこの公証役場でも一律です。
具体的には次の3種類の手数料を合計した費用がかかります。
①目的の価額による手数料
目的の価額とは、その合意に含まれる利益の金額です。養育費であれば、支払う養育費の総額で計算しますが、10年が上限とされます。たとえば、5歳の子供の養育費として毎月3万円を20歳まで支払う合意の場合、3万円×12か月×10年=360万円が目的の価額となります。これに対応する手数料は1万1000円です。下記参考条文の最後の表をご覧ください。
②正本等の交付手数料
署名押印をして完成した公正証書原本は公証役場に保管され、当事者はその写しである正本の交付を受けることになります。ここで1枚250円の手数料がかかります。
③公正証書の枚数による手数料
公正証書が4枚を超えると、超える分に1枚250円の手数料がかかります。
4.重要なのは合意内容を作る段階
公正証書の作成方法は慎重な確認作業でできていますが、性質は事務的なものです。合意内容さえ固まっていれば、淡々と進めていくだけです。
しかし、合意内容が実は十分納得いっていないものだったり、よく考えていないところがあったりすると大変です。作成途中で気が変わるなどして中断してしまうことも珍しくはないようです。それでも、不本意な公正証書が出来上がってしまうよりはましだと言えます。
そのようなことがないよう、公正証書の申し込みをする前の合意形成を確実にしておかなければならないのです。公証人はこの部分にはノータッチですから、自分たちで話し合うのが難しい場合には、是非弁護士への相談を検討なさってください。
弁護士が交渉を受任して合意をまとめた場合には、公正証書の作成手続も弁護士が進めることができますから、よりご負担の少ない形で最良の結果を残すことが可能です。
- 養育費の公正証書の作成について弁護士にご相談をされたい方は、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の無料法律相談をご覧ください。
参考条文
「公証人手数料令」
(法律行為に係る証書の作成の手数料の原則)
第九条法律行為に係る証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
第十三条 法律行為が定期の給付を目的とするときは、その給付の価額は、全期間の給付の価額の総額とする。ただし、動産の賃貸借及び雇用については五年間、その他の法律行為については十年間の給付の価額の総額を超えることができない。
2 前項の定期の給付につき期間の定めがないときは、その給付の価額は、同項ただし書に規定する法律行為の別に従いそれぞれの期間の給付の価額の総額とする。
3 第一項の法律行為につき当事者がするべき給付がいずれも金銭を目的とするものでない場合であって、相手方がするべき給付が定期のものでないときは、当該相手方がするべき給付の価額は、定期の給付の価額と同一とみなす。
(証書の枚数による加算)
第二十五条 法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により四枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、三枚)を超えるときは、超える一枚ごとに二百五十円を加算する。
(正本等の交付)
第四十条 証書の正本若しくは謄本、証書の附属書類の謄本又は定款若しくはその附属書類の謄本の交付についての手数料の額は、一枚について二百五十円とする。
別表(第九条、第十七条、第十九条関係)
|
番号 |
法律行為の目的の価額 |
金額 |
|
一 |
百万円以下のもの |
五千円 |
|
二 |
百万円を超え二百万円以下のもの |
七千円 |
|
三 |
二百万円を超え五百万円以下のもの |
一万千円 |
|
四 |
五百万円を超え千万円以下のもの |
一万七千円 |
|
五 |
千万円を超え三千万円以下のもの |
二万三千円 |
|
六 |
三千万円を超え五千万円以下のもの |
二万九千円 |
|
七 |
五千万円を超え一億円以下のもの |
四万三千円 |
|
八 |
一億円を超え三億円以下のもの |
四万三千円に超過額五千万円までごとに一万三千円を加算した額 |
|
九 |
三億円を超え十億円以下のもの |
九万五千円に超過額五千万円までごとに一万千円を加算した額 |
|
十 |
十億円を超えるもの |
二十四万九千円に超過額五千万円までごとに八千円を加算した額 |