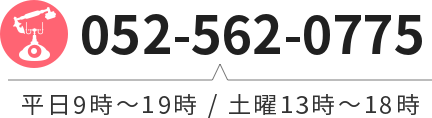養育費には教育費も含まれますが、相場となる算定表では公立高校の学費分しか見込まれていません。それに加えて大学の学費との差額分まで負担してもらうには、相手が大学への進学を承諾していたなど、一定の事情が必要です。
入学金など一時的に必要になる費用については、協議条項を入れておきましょう。何も定めておかずに後から請求しても、認められない可能性が高いです。

目次
解説
1.養育費と学費
(1)養育費には教育費が含まれている
養育費は、子供が自分の力で収入を得て一人前に生活していけるようになるまで養育するのに必要な費用です。
そこで、養育費には衣食住の費用のほかに、教育費も含まれます。ただ、教育費にいくらかかるかは、家庭により、また年齢により様々です。家庭裁判所では、多数の事案を高速に処理するため、年齢を二つに分けて、それぞれ一定の教育費を子供に必要な生活費としています。
①0歳から14歳
公立中学校の子がいる世帯の年間平均収入に対する公立中学校の学校教育費相当額
②15歳から19歳
公立高等学校の子がいる世帯の年間平均収入に対する公立高等学校の学校教育費相当額
これを考慮して子供の生活費が大人の生活費に対して占める割合を定め、親の基礎収入に掛けて養育費を算出しています。その計算結果を表に示したものが養育費算定表です。
- 養育費の計算方法については「よくある質問:養育費の計算方法を教えてください。」もご参照ください。
- 養育費算定表については「よくある質問:養育費算定表とは?養育費算定表の見方を弁護士が解説します。」もご参照ください。
(2)大学の学費は分担してもらえるか
上で述べた公立中学の学費や公立高校の学費を超える費用、たとえば私立の学費、塾の費用、大学の学費などについては、義務者(養育費を払う方)が当然に分担すべきものとはいえません。家庭裁判所では、次のような場合に分担すべきと判断しています。
①義務者がその教育を承諾していた場合
承諾は黙示のものでもよいです。離婚の時点ですでに進学している学校については、通常は承諾していたと認められるでしょう。
②義務者の収入・学歴・地位などからその教育費を負担するのが相当といえる場合
たとえば義務者自身も大学を卒業しており、大卒相当の職に就き大卒相当の収入を得ているという状況があれば、子供の大学進学に伴う費用は分担すべきと判断されやすくなります。
なお、大学の学費を分担すべきと判断されるケースでは、養育費の期間自体もそれに合わせ、大学卒業までの養育費を認めることが多いです。
- 養育費をいつまでもらえるかについては「養育費は何歳から何歳までもらえますか。大学に進学した場合はどうなりますか。」もご参照ください。
(3)国立大学と私立大学の違い
私立大学の場合、大学であるという点と私立であるという点で、二重に公立高校の学費より高額です。そのいずれについても義務者が承諾していたなどの事情がなければ、私立大学の学費の分担を求めるのは難しいでしょう。
(4)大学の学費の分担割合
家庭裁判所では、義務者も大学の学費を分担すべきだと判断したとしても、その全額を支払えとは言いません。
まず、すでに公立高校の学費分は算定表に含まれていますから、それとの差額だけが問題となります。
公立高校の学費分とは、具体的には年間25万9342円です(2019年12月に新算定表になった際に引き下げられています)。実際にかかっている大学の学費、またはかかる見込みの学費からこの額を引いた差額を分担することになります。
次に分担の割合ですが、通常の養育費算定と異なり、収入に応じてきっちり按分するわけではなく、夫婦で半々をベースに、どの程度の割合で分担させるのが相当か、という見地から判断されています。場合により、子供自身も奨学金やアルバイトで自分の学費を一部負担すべきだと判断されることもあります。
(5)大学の学費を考慮した判例
平成27年4月22日大阪高裁決定
|
・私立大学に通っている子供の学費が問題となったケースです。 ・義務者が大学進学を了承していたことが認定され、満22歳に達する年の翌年の3月までの養育費が認められています。 ・しかし、私立大学への進学までは了承していなかったとして、国立大学の学費の分担を検討しています。 ・国立大学の学費から公立高校の学費を引いた差額は約33万円でした。 ・その分担割合について、次のように述べて判断しました。
「当事者双方の収入等からすると,仮に,当事者双方が離婚していなかったとしても,当事者双方の収入で長女の学費等の全額を賄うのは困難であり,長女自身においても,奨学金を受けあるいはアルバイトをするなどして学費等の一部を負担せざるを得なかったであろうことが推認されることなどからすれば,上記超過額のうち,抗告人が負担すべきものは,その3分の1とするのが相当である。」
・結果的に、算定表の金額+9000円(月額)の養育費となりました。 |
2.入学金などの特別の費用
(1)算定表では考慮されない
算定表で出てくる養育費の金額は、それだけ払っていれば子供に対する養育の責任を金銭的に果たしていると言える性質のものです。教育費も含む子供の生活費全般がその金額に含まれていることになります。
したがって、入学金や医療費など一時的に発生する特別の費用が必要になったとしても、それは毎月の養育費の中から捻出すべきものだということになってしまいます。
(2)協議条項を作っておくのが有効
養育費を協議や調停で定める場合には、柔軟な内容にすることが可能ですから、そうした突発的な費用についても条項を設けることができます。
特別の費用が具体的に予測できるものであるならば、できるだけ金額も入れた支払義務の形にすることが望ましいでしょう。
そうでなくとも、協議条項を入れておくべきです。協議条項とは、「~については、誠実に協議する。」「~のときは、その費用の負担について、当事者間で別途協議する。」などの書き方で、将来それが問題になった際には互いに協議する義務を負うというものです。
このような協議条項を置くということは、その問題についてはその時点の合意の前提に含めないということでもあります。したがって、事情変更が認められやすく、任意に応じてもらえなくても、増額請求が認められやすくなるという効果もあります。
- 養育費の計算・金額の決め方についてさらに詳しく知りたい方は、養育費の計算のよくあるご質問をご覧ください。
- 養育費を取り決めたい方、公正証書を作成されたい方は、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の養育費の請求・調停のサービスをご覧ください。
- 養育費の計算や金額等について弁護士にご相談をされたい方は、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の無料法律相談をご覧ください。